すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
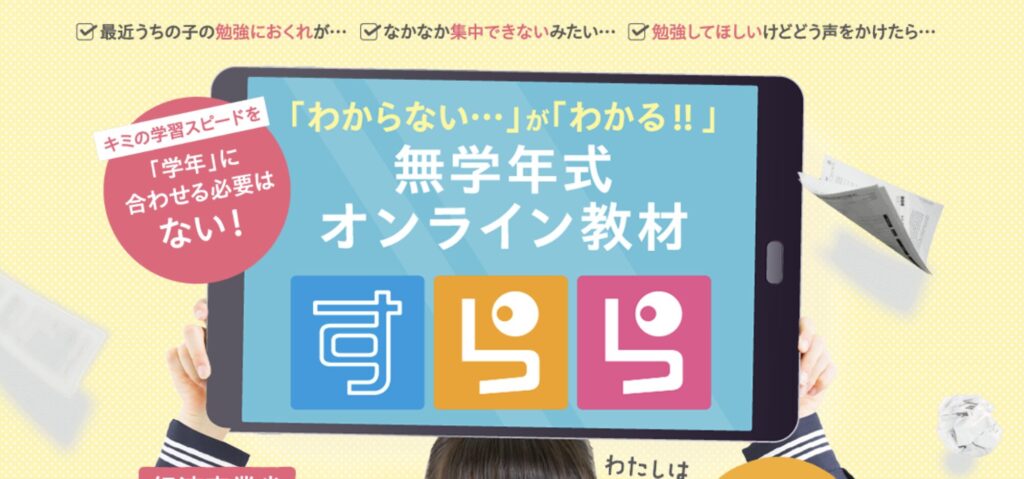
不登校のお子さまが学校に通わなくても、学習を続けられる環境を提供することは非常に重要です。
「すらら」は、家庭での学習支援を行いながら、学校に通うことができないお子さまに対して、学習の進捗を記録し、出席扱いになる可能性があるという特長を持っています。
その理由は、学習内容の充実度や継続的なサポート体制にあります。以下に、出席扱いになる主な理由を説明します。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
「すらら」は、学習の質が高く、きちんとした学習の証拠を提供できるシステムを備えています。
まず、学習内容と進捗に関する「客観的な学習記録レポート」を学校に提出することができます。
これにより、学校側にお子さまが自宅学習をしている証拠を示し、学習活動の透明性を保つことができます。
また、保護者が手間をかけることなく、自動的に学習状況が可視化される仕組みがあります。
これにより、学校側はお子さまの学習状況を正確に把握でき、安心して出席扱いを認める材料となります。
これらの要素が相まって、学校との信頼関係を構築しやすくなります。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
「すらら」は、学習の質が高く、きちんとした学習の証拠を提供できるシステムを備えています。
まず、学習内容と進捗に関する「客観的な学習記録レポート」を学校に提出することができます。
これにより、学校側にお子さまが自宅学習をしている証拠を示し、学習活動の透明性を保つことができます。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
また、保護者が手間をかけることなく、自動的に学習状況が可視化される仕組みがあります。
これにより、学校側はお子さまの学習状況を正確に把握でき、安心して出席扱いを認める材料となります。
これらの要素が相まって、学校との信頼関係を構築しやすくなります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
「すらら」では、学習の計画性と継続性を確保できるサポート体制があります。
すららでは、専任のコーチが個別に学習計画を立て、継続的な支援を提供します。
学習プランは、お子さまのペースや理解度に合わせて柔軟に変更され、無理なく学び続けることができます。
このような個別最適な学習計画と継続支援が組み合わさることで、学校側にはお子さまが着実に学習を進めていることを証明でき、出席扱いとして認められやすくなります。
すららは、学習の進捗をサポートするだけでなく、個別のニーズに応じた支援を提供する点でも優れた選択肢と言えます。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
「すらら」では、学習の計画性と継続性を確保できるサポート体制があります。
すららでは、専任のコーチが個別に学習計画を立て、継続的な支援を提供します。
学習プランは、お子さまのペースや理解度に合わせて柔軟に変更され、無理なく学び続けることができます。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
「すらら」では、専任のコーチが個別に学習計画を作成し、継続的にサポートを行います。
お子さま一人ひとりに最適な計画が立てられ、進捗に合わせたサポートが受けられるため、学習がスムーズに進みます。
このアプローチは、特に不登校のお子さまにとって非常に効果的で、学習に対する自信を持たせてくれます。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
「すらら」では無学年式の学習システムを採用しており、学年に縛られることなく、お子さまの理解度やペースに合わせて学習を進められます。
これにより、学習の遅れがあってもその分野をしっかりと理解できるまで学び、また、進度が早い場合には次のステップに進むことができます。
お子さまのペースに合わせて柔軟に対応できるので、焦らずに学習を続けることができます。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
「すらら」は家庭、学校、そしてすららの三者がしっかりと連携できるサポート体制を提供しています。
これにより、お子さまの学習状況や進捗が家庭だけでなく学校側にも伝わり、学校と家庭で協力して支援できる環境が整います。
以下に、具体的なサポート内容を紹介します。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
「すらら」は、学校に提出するために必要な書類の準備方法を案内してくれます。
これにより、保護者の負担を軽減し、書類作成にかかる時間や手間を省くことができます。
書類をどのように提出するか、必要な情報をどのようにまとめるかなど、親身なサポートが受けられます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
「すらら」では、専任コーチが学習レポートを提出する際のサポートをしてくれます。
レポートには、進捗や学習内容が詳細に記載されており、学校側に提出する際にはフォーマットの用意もしてくれます。
このレポートを通じて、学校にお子さまの学習状況を正確に伝えることができます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
「すらら」は、担任や校長との連絡をスムーズに行うためのサポートを提供します。
必要に応じて、連絡先や連絡方法を案内したり、コミュニケーションを円滑に進めるためのアドバイスをしてくれます。
このサポートにより、学校と家庭が密に連携し、お子さまの学習をより効果的に支援することができます。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
「すらら」は、文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績を持っています。
これにより、不登校の児童・生徒に対しても、学校に通わずに学習を進めることができると認められています。
以下に、具体的な実績を紹介します。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
「すらら」は、全国の教育委員会や学校と連携しており、その信頼性が高い教材として認められています。
これにより、学校と「すらら」を通じた学習支援が進んでおり、個別の学習支援が充実しています。
地域や学校ごとに対応が異なる場合もありますが、すららは広範なネットワークでサポートしています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
「すらら」は、文部科学省の認可を受けて公式に「不登校支援教材」として利用されています。
これは、学校に通うことが難しい生徒に対して、学習の機会を提供することを目的とした認定です。
不登校の生徒でも安心して利用できるように設計されており、学習が途切れないようサポートされています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
「すらら」の学習環境は、学校のカリキュラムに準じており、そのため学校に準ずると認められやすいです。
これにより、家庭での学習環境が学校での学びと同等の効果を得られるとされています。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
「すらら」の学習内容は、学校の学習指導要領に基づいて構成されています。
このため、学校の授業に合わせた形で学習を進めることができ、必要な知識やスキルを効率的に習得することができます。
また、学習の進捗が学校での評価と一致するよう設計されています。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
「すらら」には、学習の評価とフィードバックがシステムとして組み込まれています。
これにより、生徒の学習状況がリアルタイムで把握でき、進捗に応じたフィードバックが得られます。
評価は、学校での学習と連動しており、保護者や教師も学習の進捗を確認しやすくなっています。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
「すらら」を利用することで、不登校の状態でも出席扱いになることがあります。
このセクションでは、出席扱いを申請するための具体的な方法と必要な書類について解説します。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いの申請をするためには、まず担任や学校に相談することが重要です。
学校側との協力が必要となるため、学校の指示に従って手続きを進めましょう。
相談を通じて、どのようなサポートを受けることができるかを確認することができます。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いの申請に必要な書類や条件は、学校によって異なる場合があります。
「すらら」を使った学習が認められるために必要な書類や手続きについて、学校に問い合わせて事前に確認することをおすすめします。
また、出席扱いを受けるためには、学習状況の記録や進捗を提出することが求められることもあります。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
場合によっては、医師の診断書や意見書が求められることがあります。
これにより、不登校の理由や学習の継続が望ましいことを証明するためのサポートを受けることができます。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
不登校の理由が精神的または身体的な要因による場合、学校から診断書を提出するよう求められることがあります。
診断書には、不登校の原因や学習継続が重要である旨が記載されることが一般的です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書は、精神科、心療内科、小児科などの専門医から取得できます。
医師には、現在の不登校の状態と学習継続の重要性を記載してもらう必要があります。
この診断書が提出されることで、学校側は生徒の状況をより正確に理解し、適切な対応を取ることができるようになります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いを申請する際には、すららの学習記録を学校に提出することが重要です。
これにより、学校は自宅学習をしていることを証明する材料を得ることができます。
すららの学習進捗レポートには、学習内容、進捗状況、学習時間などが詳細に記録されており、学校側にとっては信頼性のある資料となります。
学校に提出することで、出席扱い申請を進めるために必要な証拠が整い、申請がスムーズに進行します。
このレポートは定期的に更新されるため、保護者が進捗状況を確認し、学校に報告できる形で活用できます。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららでは、学習進捗レポートを専用システムからダウンロードすることができます。
このレポートには、学習内容、進捗状況、評価結果などが詳細に記録されており、学校側に対して正確な情報を提供することができます。
レポートを担任または校長先生に提出することで、学校側は児童の学習状況を確認でき、出席扱いの判断に必要な証拠となります。
このプロセスが完了すれば、学習が進んでいることが証明され、正式に出席扱いの申請を行うことができます。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いを申請するためには、学校側で「出席扱い申請書」を作成する必要があります。
この申請書には、学習の進捗状況や学校側が必要とする情報を記入します。
保護者は学校と協力して、必要な書類を準備し、申請書を作成するサポートを行います。
保護者のサポートによって、申請書の作成がスムーズに進み、出席扱いの手続きが確実に行われます。
申請書が完了すると、学校側はその内容を元に出席扱いの申請を進めることができます。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
すららを使用している場合の出席扱い申請は、最終的に学校と教育委員会の承認を得る必要があります。
学校側で必要な書類が整った後、出席扱いが認められるかどうかの最終決定が行われます。
学校長がその申請内容を確認し、出席扱いを決定することが一般的です。
学校長は学習進捗レポートや申請書類を元に判断を行い、適切な判断を下します。
もし必要があれば、教育委員会に申請を行うこともあり、この場合は学校側と連携して進めていきます。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
最終的な出席扱いの決定は、学校長の承認によって行われます。
学校長は、提出された学習記録や申請書類を元に出席扱いの申請を審査し、判断を下します。
この承認を得ることで、出席扱いが正式に認められ、児童は学校の出席扱いとして扱われます。
学校側は、出席扱いに関する詳細な手続きとともに、学習の継続をサポートする体制を整えることが重要です。
承認後、出席扱いが記録に反映され、正式に学校に通っていることが認められます。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
出席扱いを申請する際に、教育委員会の承認が必要な場合があります。
この場合、学校側と密に連携し、教育委員会に必要な書類を提出する手続きを進めます。
教育委員会が関与することで、申請はさらに正式なものとなり、地域や自治体の教育方針に基づいて出席扱いが決定されます。
学校と教育委員会の協力により、出席扱いの申請が確実に進められます。
学校と教育委員会の連携を大切にし、適切な手続きを踏むことで、出席扱いが無事に決まるようになります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校の子どもにとって、出席扱いを受けることは大きな意味があります。
すららを使った学習で出席扱いとなると、学習面や進学面においてさまざまなメリットがあります。
この記事では、出席扱いを認めてもらうことによる具体的なメリットを紹介します。
これらのメリットは、子ども自身の成長だけでなく、保護者の心の負担軽減にもつながります。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
不登校になると、内申点が下がるのではないかという不安があります。
しかし、出席扱いを受けることで、実際の出席日数を積み上げることができ、内申点の評価にも良い影響を与えることが可能です。
すららを使った学習を積極的に続けることで、学校に出席していなくても学習を進めている証拠を作ることができ、評価を下げずに済むことになります。
特に進学においては、内申点が重要な要素となるため、この点は非常に大きなメリットです。
中学や高校への進学において、選択肢を広げることができます。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
出席日数が増えることで、内申点が下がりにくくなるメリットがあります。
学校側は出席状況を評価基準としているため、欠席が多いと内申点が低くなる可能性がありますが、すららで学習を継続することで、出席日数をしっかりとカウントできます。
これにより、出席日数に関する心配が減り、内申点への悪影響を防ぐことができます。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席扱いを受けることで、進学に向けた選択肢が広がります。
特に中学や高校の進学においては、内申点が重要な評価基準となるため、出席日数をクリアしていることで、進学先の幅が広がります。
すららで学習を続けることで、進学における不安を減らすことができます。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校であると、授業の遅れを感じることが多いです。
しかし、すららで継続的に学習を進めることで、授業の進捗に取り残されることなく学び続けることができます。
これにより、「遅れている」「取り戻せない」という不安を抱えることが減り、学習に対する自信がついてきます。
また、学習が進むことで、自己肯定感も向上し、子ども自身のモチベーションが高まります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららは学習のペースを個別に調整することができ、子ども自身の進度に合わせた学習が可能です。
そのため、遅れを取ることなく学習を続けることができ、「取り戻せない」という不安を感じることなく学習を続けられます。
これにより、授業の遅れや進捗の差を気にせず、安心して学習を続けられます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
すららを使うことで、家庭での学習環境が整い、子どもは自分のペースで学習できます。
この環境が整うことで、学習に対する不安が軽減し、自己肯定感の低下を防ぐことができます。
自己肯定感が高まると、学習に対してもポジティブな気持ちで取り組むことができ、子どもの成長をサポートします。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを持つ親は、学習のサポートや進学への不安などで心の負担が大きくなることがあります。
しかし、すららを活用することで、学校・家庭・コーチが連携し、学習をサポートする体制が整います。
これにより、親一人で不安を抱える必要がなく、心の負担を軽減することができます。
親が学校やコーチと連携することで、学習がスムーズに進み、安心して子どもの学びをサポートすることができます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららでは、学校、家庭、コーチが協力し合い、子どもの学習をサポートします。
これにより、親が学習の進捗や困難に一人で対応する必要がなくなり、ストレスが軽減されます。
家庭と学校、そしてすららコーチとの連携で、学習サポートが充実し、親の負担が減ります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを使って不登校でも出席扱いを認めてもらうためには、いくつかの注意点があります。
この記事では、出席扱いを認めてもらうために必要な注意点について紹介します。
出席扱いを認めてもらうためには、学校や医師との連携が重要となります。
慎重に対応し、適切な手順を踏んで進めることが大切です。
これらの注意点を理解し、準備を進めていくことで、よりスムーズに出席扱いを認めてもらうことが可能になります。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを受けるためには、学校側の理解と協力が不可欠です。
すららは文部科学省のガイドラインに基づく教材であることを、学校側に丁寧に説明する必要があります。
これにより、学校がすららの利用を正当な学習方法として認めてくれる可能性が高まります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参し、具体的にどのような内容で学習を進めているかを示すと効果的です。
担任だけでなく、教頭や校長にも早めに相談することで、よりスムーズに進めることができます。
学校の理解を得ることで、出席扱いが認められやすくなり、子どもの学習環境も安定します。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
学校側にすららが文科省のガイドラインに基づく教材であることを説明し、正式な学習教材としての位置づけを理解してもらうことが大切です。
この説明がしっかりとなされることで、学校側がすららを学習の一環として認める可能性が高くなります。
これにより、出席扱いが認められる道が開け、子どもは学習の遅れを取り戻すことができるようになります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
すららの教材やサポートの詳細をまとめた資料を学校に持参することで、学校側に理解してもらいやすくなります。
また、担任の先生だけでなく、教頭や校長にも早めに相談することで、学校全体でのサポートが得やすくなります。
早期に学校側と連携を取ることが、出席扱いをスムーズに進める鍵となります。
そのため、すららの利用に関する書類や説明資料を準備し、学校側に積極的に説明することが重要です。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の原因が体調不良や精神的な理由の場合、医師の診断書や意見書が求められることが多いです。
この場合、医師にお願いして診断書や意見書を取得する必要があります。
その際、診断書には不登校の状態や学習継続の必要性が記載されることが望ましいです。
医師が診断書を作成する際に、前向きな内容をお願いすることが重要です。
診断書や意見書は、学校側に対して不登校の理由を明確に伝えるための大切な資料となります。
医師に状況を詳しく説明し、必要な情報を盛り込んでもらうことで、学校側からの理解を得やすくなります。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
体調不良や精神的な理由で不登校の場合、学校側から診断書や意見書の提出を求められることがあります。
これにより、学校が出席扱いを認めるための重要な資料となります。
診断書には、医師が記載した学習継続の必要性や状態をもとに、学校が判断することができます。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を依頼する際には、通っている小児科や心療内科に「出席扱いのための診断書が必要である」と伝えることが重要です。
その際に、診断書が出席扱いをサポートする目的であることを明確にすることで、より適切な内容が記載されます。
また、出席扱いを支援するために、医師からの具体的なアドバイスを受けることも役立ちます。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書を作成してもらう際、家庭での学習の状況や子どもの学習意欲についても具体的に説明することが大切です。
これにより、医師が前向きな内容で診断書を記載してくれる可能性が高まります。
前向きな内容が記載された診断書は、学校側に出席扱いを認めてもらうために非常に有益です。
診断書には、学習意欲を持ち続けていることが記載されることで、出席扱いを受けるための根拠が強化されます。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いを受けるためには、学習内容が学校の授業に準じたものである必要があります。
単なる自習ではなく、学校での授業内容に基づく学習が求められます。
例えば、数学や国語、英語など、主要教科の内容を進める際には、学校の指導要領に準じた教材を使用することが重要です。
また、学習時間についても、学校の授業時間に近い形で進めることが求められます。
目安としては、1日2〜3時間程度が理想とされています。
全教科をバランスよく進めることが重要です。
特定の教科のみの学習だと、学校側が出席扱いを認めない場合もあるため、主要教科に偏りすぎず、全体的に学習を進めることが求められます。
このように、学校の学習指導要領に沿った学習を心掛けることで、出席扱いが認められやすくなります。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
単なる自習での学習は、出席扱いの認定には不十分です。
出席扱いを受けるためには、学校の授業に準じた内容を学習することが必要です。
すららは、学校の授業に基づいた内容を提供しているため、出席扱いを認めてもらいやすいです。
自習だけでは学習内容が不明確になるため、学校のカリキュラムに合わせた学習が重要です。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いを受けるためには、学習時間が学校の授業時間に近い形であることが求められます。
目安としては、1日2〜3時間程度の学習が望ましいとされています。
これにより、学校での授業時間と同様の学習量が確保され、出席扱いを認めてもらう根拠になります。
時間を守ることで、学習が適切に進んでいることを示すことができ、学校側に安心感を与えることができます。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
全教科をバランスよく進めることも出席扱いを受けるためには非常に重要です。
特定の教科に偏ることなく、全ての教科を進めることが求められます。
主要教科だけに集中するのではなく、副教科やその他の教科もきちんと学習することが出席扱いを認めてもらうためのポイントです。
これにより、学校の学習指導要領に基づいた学習が実践されていることを証明できます。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いを受けるためには、学校との定期的なコミュニケーションが不可欠です。
学習状況を学校と家庭で共有することが求められ、学校側からの確認や進捗状況の報告を行う必要があります。
月に1回は学習レポートを提出することが一般的であり、すららではそのレポートを簡単にダウンロードして提出することができます。
学校側から求められる場合は、家庭訪問や面談にも対応することが重要です。
また、担任の先生とはこまめにメールや電話で進捗を共有し、学校との連携を密に取ることが大切です。
これにより、学校側と円滑なコミュニケーションが築かれ、出席扱いが認められる可能性が高まります。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
出席扱いを受けるためには、学校と家庭で学習状況を定期的に共有することが大切です。
学校側が学習の進捗状況を把握することで、出席扱いの認定がスムーズに進みます。
そのため、家庭でも積極的に学習状況を報告し、学校と協力して進めることが必要です。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららでは、月に1回学習レポートをダウンロードして提出することが推奨されています。
学習レポートには進捗状況が記載されており、学校に提出することで、学習の進行状況を明確に伝えることができます。
これにより、学校側から学習の進捗に対する理解を得やすくなり、出席扱いが認められやすくなります。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応することが重要です。
学校側としっかりコミュニケーションを取ることで、出席扱いがスムーズに進む可能性が高くなります。
家庭訪問や面談の際には、学習の進捗状況や子どもの状態について詳しく話し合い、学校との連携を深めましょう。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
担任の先生とはこまめにメールや電話で進捗を共有すると良いです。
これにより、学校と家庭の間での情報交換が円滑になり、出席扱いが認められる道が開けます。
進捗状況を頻繁に伝えることで、学校側も安心して子どもの学習状況を把握できます。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
場合によっては、教育委員会への申請が必要となることがあります。
教育委員会に提出するための資料は、学校と相談しながら進めていくことが重要です。
学校との連携をしっかりと取り、必要な資料を整えることが、スムーズに申請を進める鍵となります。
申請には、学習状況や学習内容を証明する書類が必要となることが多いため、すららの学習記録や進捗レポートが役立ちます。
また、教育委員会によっては、特別な対応や条件が求められる場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。
そのため、学校側と事前にしっかりと話し合い、必要な書類を揃えて提出する準備を進めましょう。
教育委員会への申請が必要かどうかは、地域によって異なるため、学校側との協力が不可欠です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
場合によっては、教育委員会への申請が必要となることがあります。
教育委員会に提出するための資料は、学校と相談しながら進めていくことが重要です。
申請に際しては、学習状況や学習内容を証明する書類が必要となることが多いため、すららの学習記録や進捗レポートが役立ちます。
教育委員会に対しては、学習の進捗が「学校に準じた内容」であることを証明する資料が求められる場合もあります。
そのため、学校との連携をしっかりと取り、必要な資料を整えて申請する準備を進めましょう。
また、教育委員会によっては、特別な対応や条件が求められる場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。
教育委員会への申請が必要かどうかは、地域によって異なるため、学校側との協力が不可欠です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
不登校の生徒でも、出席扱いを認めてもらえる可能性があることをご存知でしょうか?
すららは、学習進捗が確認できるツールを提供することで、不登校の生徒に対しても出席扱いが認められる可能性を高めます。
ここでは、出席扱いを認めてもらうために学校と連携し、適切なアプローチを取るための成功ポイントを紹介します。
出席扱いを認めてもらうためには、学校との信頼関係を築き、しっかりとした学習態度を示すことが重要です。
以下のポイントを参考にして、スムーズな申請を目指しましょう。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
出席扱いを認めてもらうためには、学校にすららを使った他の学校での実績を紹介することが非常に効果的です。
すららの使用実績がある学校が増えているため、その前例を活用することで、学校側に説得力を持たせることができます。
実績紹介が具体的に示されていると、学校側も「すらら」が有効な教材であると認識しやすくなります。
これにより、出席扱いを受け入れてもらいやすくなるでしょう。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
学校側に「すらら」を導入して出席扱いを認められた学校の事例を紹介することは、非常に効果的なアプローチです。
実際に成功した事例を具体的に伝えることで、学校側が積極的に導入を考えやすくなります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトには他の学校での実績が紹介されています。これをプリントアウトして学校に持参すれば、事例に基づいた説得力が増します。
公式サイトに載っている事例を参照することで、学校側も納得しやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いを認めてもらうためには、本人が学習にどれだけ意欲的に取り組んでいるかを示すことが非常に重要です。
すららを使った学習は、進捗が記録されるため、本人がどれだけ努力しているかを具体的に示すことができます。
学校側も、学習に対する意欲があることを確認できれば、出席扱いを認めるハードルが低くなるでしょう。
学習の結果だけでなく、学習に対する取り組み姿勢も非常に重要です。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
本人が自分で書いた学習の感想や目標を提出することは、非常に効果的です。
これにより、学校側は生徒が学習に対して前向きに取り組んでいることを確認できるため、出席扱いの認定が得られやすくなります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
面談がある際には、本人も積極的に参加し、どれだけ頑張って学習しているかを直接伝えることが大切です。
学校側は、本人が積極的に参加することで、その意欲を感じ取り、出席扱いを検討しやすくなります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いを認めてもらうためには、無理なく継続できる学習計画を立てることが非常に重要です。
特に、不登校の生徒は学習への取り組みが中断しがちですが、無理なく続けられる計画を立てることで、学習が持続し、学校側からの信頼も得やすくなります。
計画を立てる際には、本人のペースに合わせることが大切です。
無理に多くの時間を詰め込むことは、負担となり逆効果になることもあるため、現実的かつ負担が少ない計画が求められます。
すららのツールを活用して、無理なく進められるスケジュールを作成し、少しずつ学習を積み重ねていくことが大切です。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
学習計画は、本人のペースに合わせることが最も重要です。
本人にとって過度な負担をかけることなく、スムーズに学習を進められるように計画を立てましょう。
これによって、学習の継続が促され、学校側にも着実に学習を進めているという信頼を与えることができます。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららには学習をサポートするコーチがいるため、そのコーチに相談しながら計画を立てることができます。
コーチは、実際の学習進捗を見ながら、最も効果的な学習スケジュールを提案してくれるため、無理なく続けられる計画を作る手助けをしてくれます。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
「すららコーチ」をフル活用することは、出席扱いを認めてもらうために非常に重要です。
コーチは学習計画の策定だけでなく、必要な学習証明やレポートの作成をサポートしてくれます。
特に、学校に提出する学習の進捗状況やレポートは、すららコーチが専門的にサポートしてくれるため、心強い存在となります。
コーチと協力することで、出席扱いの申請に必要な書類や証明書類を効率よく準備できるため、申請手続きがスムーズに進みます。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
出席扱いを申請するためには、学習の進捗を証明するレポートが必要ですが、これをコーチがサポートしてくれます。
コーチが作成するレポートは、学校が求める基準に沿った内容であるため、申請時に大きな助けとなります。
必要な証明書類やレポートが整うことで、申請がスムーズに進むでしょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららを利用して不登校でも出席扱いを認めてもらうためのポイントや注意点に関する情報を提供する中で、よく寄せられる質問をいくつか取り上げます。
これから紹介する質問とその回答を参考に、すららの利用に関する理解を深めましょう。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すらら うざい」という口コミが存在する理由としては、学習の進捗管理が厳格である点や、学習プランの進行が思うように進まない場合にストレスを感じることがあるためです。
特に、不登校の子どもたちにとって、進捗状況をきちんと報告したり、定期的な学習を強制されたりすることが負担になり、「うざい」と感じる原因になっていることがあります。
また、学習内容の指示が一律であるため、個々のペースに合わせた学習が難しい場合も、利用者が不快感を感じる要因となることがあります。
これらの批判的な意見は、一部のユーザーにとっての感想であり、全ての利用者が同様に感じるわけではありません。
ユーザーによっては、しっかりとしたサポートや進捗管理を評価している場合もあります。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららの発達障害コースは、特別なニーズを持つ子どもたちのために提供される学習プランです。
このコースは、通常の学習プランとは異なり、個別の支援が充実しているため、子どものペースに合わせて学習を進めることが可能です。
料金プランは一般的なすららのプランと異なり、個別サポートが含まれているため、若干高めになることがあります。
具体的な料金については、公式サイトで詳細なプラン内容を確認することをお勧めします。
なお、発達障害コースは、利用者一人一人の状況に応じたサポートを受けられるため、その分柔軟な対応が可能です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららのタブレット学習は、不登校の子どもに対しても一定の学習進捗を証明できるため、出席扱いになる可能性があります。
ただし、出席扱いを認めてもらうためには、学校と事前に連絡を取り、出席の扱いを申請する必要があります。
すららのタブレット学習は、自宅学習をサポートするツールとして活用できるため、学習が進むにつれて学校側に報告できる進捗状況が整います。
学校に出席扱いを認めてもらうためには、定期的な学習報告が必要であり、すららの進捗レポートを学校に提出することが求められます。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードは、特定の時期に提供されるプロモーションコードで、料金の割引や特典が適用されるものです。
キャンペーンコードを利用する際には、すららの公式サイトやお知らせメールに記載されているコードを確認し、申し込み時に入力します。
キャンペーンコードは期限が設定されている場合もあるため、利用期限を過ぎないように注意が必要です。
割引率や特典内容はキャンペーンによって異なるため、公式サイトをチェックして、お得な期間を逃さず活用することをおすすめします。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会する場合、まずは公式サイトまたはアプリからログインし、アカウント設定を開きます。
退会手続きに関しては、サポートセンターに問い合わせをするか、専用の退会フォームから手続きを進めることができます。
退会手続きが完了する前に、残りの利用料金の支払いが必要となる場合があるため、確認を怠らないようにしましょう。
また、退会後に再度利用する場合、再登録が必要となるため、注意が必要です。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららを利用する際には、入会金と毎月の受講料が基本的な費用となりますが、それ以外にも一部オプション料金がかかる場合があります。
例えば、追加の学習教材を購入したり、特別なサポートサービスを利用する場合は、別途料金が発生することがあります。
また、キャンペーンや割引プランが適用されることもあるため、定期的に公式サイトやお知らせをチェックし、最新の料金情報を確認することをお勧めします。
基本的な受講料以外の費用は、オプションに依存するため、個別のプランやサービス内容に合わせて検討する必要があります。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららの基本的なプランは、1人の受講者に対して提供されるものですが、兄弟で一緒に使うことができるかどうかは、利用契約やプランによって異なる場合があります。
一般的には、追加の受講者には別途料金が必要となる場合が多いため、兄弟で利用する場合は個別にプランを契約する必要があることが多いです。
ただし、すららのサポートセンターに相談し、家族割引や特別プランの有無を確認することで、お得に利用できる可能性もあります。
兄弟での利用を検討している場合は、契約前に確認しておくと良いでしょう。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースでは、英語の学習もカバーされています。
英語の学習内容は、基礎的な英語力を身につけるためのカリキュラムが組まれており、語彙や文法、会話などを学べるプランがあります。
小学生向けには、英語の基礎を学ぶために適切なレベルで進められるコースが提供されていますので、子どもの進捗に合わせて学習ができます。
すららの英語コースは、楽しみながら学べるように工夫されており、ゲーム感覚で学べる内容も含まれています。英語に関する学習を充実させたい場合は、具体的なコース内容を確認してから選ぶことをおすすめします。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららのコーチからは、学習計画の立て方や進捗のサポートを受けることができます。
コーチは、個別の学習状況に合わせて、適切なアドバイスやアクションプランを提供してくれるため、学習が進んでいないと感じた場合でも安心して相談できます。
また、コーチは定期的に学習の進捗をチェックし、必要に応じてフィードバックを提供してくれるため、子どもが継続的に学習できる環境を整えてくれます。
さらに、すららでは、学習に関する疑問点や質問に対しても、コーチがサポートしてくれるため、モチベーションを保ちながら学習を進めやすくなります。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
不登校の子どもを持つ家庭にとって、学習の方法は非常に重要です。
特に、自宅学習が進む中で、学校に出席扱いとなるかどうかは、非常に大きな問題となります。
今回は、すららをはじめとする家庭用タブレット教材を、不登校の子どもにとってどのように役立つのか、また他の教材とどのように比較されるのかについて詳しく見ていきます。
不登校の子どもに対して出席扱いが認められる学習方法は限られていますが、家庭でできる学習方法をしっかりと選ぶことは、学びの継続と社会復帰の支援にもつながります。
それぞれの教材がどのようにサポートしているのかを理解することが、より良い選択に繋がります。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
すららは、文部科学省のガイドラインに対応したICT教材として、不登校の子どもでも「出席扱い」にできる可能性がある学習手段のひとつです。
ただし、実際に出席扱いと認めてもらうためには、いくつかの制度的な要件や学校との連携が必要です。
学校の理解を得るための丁寧な説明や、医師の診断書の提出、家庭と学校との継続的な情報共有など、準備すべきことは少なくありません。
また、すららのような教材を利用する際には、学習内容や時間が学校教育に準じていることが求められるため、コーチと相談しながら無理のない学習計画を立てることも重要です。
教育委員会への申請が必要となるケースもあるため、学校側と密に連携しながら進めることが成功の鍵です。
不登校でも前向きに学びを続けられる環境を整えることは、子ども自身の自信と将来の可能性を広げることにつながります。
すららをうまく活用しながら、家庭・学校・専門家が連携し、出席扱いの制度を有効に活かしていきましょう。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較